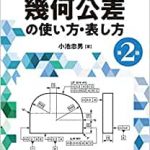受講概要
1.幾何公差の基礎知識
1.1 幾何公差を用いる意義
1.2 幾何公差の種類
1.3 用語と定義、記号と意味
1.4 データムの理解と指示方法
2.幾何公差の指示方法とその解釈
2.1 形状公差(真直度、平面度、真円度、円筒度)の指示方法と解釈
2.2 姿勢公差(平行度、直角度、傾斜度)の指示方法と解釈
2.3 位置公差(位置度、同心度、同軸度、対称度)の指示方法と解釈
2.4 輪郭度(線の輪郭度、面の輪郭度)の指示方法と解釈
2.5 振れ公差(円周振れ、全振れ)の指示方法と解釈
3.演習問題
受講形式
会場・WEB
オンラインでご参加の方は、事前にこちらでZoomの接続環境をご確認ください。
スムーズな受講のため、カメラ・マイク・スピーカーの動作をご確認ください。
受講対象
機械図面を作成する設計者
機械図面を見て製造、あるいは検査に携わる技術者
社内での機械製図規則の作成や制定に携わる技術者
予備知識
「機械製図規則」
JIS B 0001「機械製図」があれば理解が進みます。
習得知識
1)国際的に通用する「機械製図規則」の概要
2)「サイズ公差」についての基礎知識
3)「幾何公差」についての基礎知識 など
講師の言葉
今までの日本の機械図面では、もはや海外(特に欧米)では通用しません。その最大の理由は、「部品形状の表し方」にあります。今までの図面では、部品のあるべき「形状」について、「寸法」と「寸法公差」を用いた様々な指示によって表現してきましたが、形状のあり方を明確に表現するには限界がありました
現在、国際規格ISOでは「寸法」は「サイズ」と「距離」に分類し、「サイズ」に関しては「サイズ公差」で、「距離」については「形状の許容範囲」を含めて「幾何公差」を使って、図面で明確に指示するようになってきています。また、その基になるISO規格もここ数年、多くの新規制定や改定がなされ充実してきています。今後、国際的には、「幾何公差を用いた機械図面」が当たり前となることは必至ですが、しかし、残念なことに現在のJIS規格は、これにほとんど対応できていません。
そこで、このセミナーでは、日本の設計者の多くが抱いている疑問、「なぜいま“幾何公差”を用いた機械図面にしなければならないのか」を詳しく説明し、「幾何公差」の重要性について丁寧に解説します。さらに、それを用いるために必要な基礎事項もしっかり習得していただきます。是非、この機会を逃さずに、「幾何公差を用いた機械図面」の世界を知っていただき、「国際的に通用する機械図面」の作成者、あるいは理解者になっていただきたいと希望しています。
進呈
講師著書『実用設計製図 幾何公差の使い方・表し方 第2版』(日刊工業新聞社刊)を進呈します。