受講概要
1章 材料力学と強度設計の考え方
(1) ものごとの適切な進め方
(2) 設計での材料力学の目的
(3) 強度評価で重要な
4つの影響因子
(4) 強度判定の方法
(5) 破壊現象の分類
2章 応力について
(1) 応力~機械装置の破壊で
重要なのは垂直応力
(2) 発生応力を求めるための
簡単な計算式
(3) ひずみ、ポアソン比と
フックの法則
(4) 簡単な式を使った簡単な
強度評価方法
(5) 主応力と相当応力について
3章 力の流線について
(1) 力の伝達と
水の流れの似たところ
(2) 力の流線でわかる応力の大小
(3) サン・ブナンの原理
4章 応力集中と応力集中係数
(1) 応力集中係数αの定義
(2) 応力集中の発生要因と特異点
(3) 応力集中と力の流線の関係
(4) 応力集中部からの
破断面の推測の仕方
(5) 応力集中係数αの
上限値の見積り方
5章 応力集中が強度低下に及ぼす 影響と強度低下率(切欠係数)β
(1) 寸法効果について
(2) 強度低下率(切欠係数)βの定義
(3) 強度低下率(切欠係数)βと
応力集中係数αの関係
(4) 特異点での強度の把握の仕方
(5) 強度評価の結論
6章 安全率
(1) 安全率の値の定め方
~まずは,法律,業界基準
(2) 理論的な定め方(その1)
←50年前に制定
~強度と応力のばらつきが正規分布すると考えた場合
(3) 理論的な定め方(その2)
←現代の標準
~強度と応力のばらつきが対数正規分布すると考えた場合
(4) アンウィンの安全率
←100年前に制定
~有名だが、今は使わないように
7章 まとめ
受講形式
会場・WEB
オンラインでご参加の方は、事前にこちらでZoomの接続環境をご確認ください。
スムーズな受講のため、カメラ・マイク・スピーカーの動作をご確認ください。
受講対象
・機械装置の構造を設計する技術者
・機械装置の品質管理を担当する技術者
予備知識
・身の回りにある機械装置に対して、どのような力が作用しているか、
どのような現象を発生しているかを見て考えておくこと。
・数式に値を代入して計算ができること。
習得知識
1)簡単な形状の部材に、力やモーメントが作用した時の応力が計算できるようになる。
2)部材が力の作用によって破壊しないようにするための技術が身につく。
3)応力集中によって生じる強度低下への対策ができるようになる。
4)工作担当者や品質管理部門では、設計者が出図した図面を見て、強度的に大丈夫かどうか検討ができるようになる。
講師の言葉
ひとりのエンジニアが多種多様な業務を担当するようになった現在,時間を有効に使うためには、目の前の課題をできるだけ速く処理する必要があります。しかし、機械装置の構造の設計に必要な材料力学を市販の教材で勉強しようとすると、あれもこれもと書いてあるために、なかなか必要な技術習得にまで到らないのが悩みです。
このセミナーは、材料力学の初心者のために、使用頻度の低い項目は省略し、実用的な内容を抽出して構成しました。特に、設計した装置が壊れないようにすることに重点を置いていますので、仕事上の役割が一致する技術者にとっては、明日からでも即座に役立つことでしょう。
進呈
講師著書:「強度検討のミスをなくすCAEのための材料力学(日刊工業新聞社)」を進呈します。
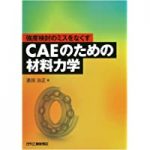
受講者の声
セミナー内容については私のまさに学習したかったことでした。今回いただいた遠田先生の本も読んでした身としては、本の内容が大きく深まりとても満足度の高い講義でした。
材料力学の基本的な計算式で十分強度検討ができるということを知ることが出来て良かった。難しいことを難しいまま考えるのではなく、簡単なことに置き換えて考えることが大切であると改めて感じた。
入社してから機械設計をやっていたのでが、強度などはあやふやな状態だったのでそこが整理できた。
簡易的に捉えて強度計算することで、詳細な強度CAEをせずとも妥当な判断が可能であることを知ることができ有益だった。
これからの設計業務で有用な講義となりました。ありがとうございます。